夏を過ぎて秋に入ったころから過去問に取り組む受験生が多くなってきます。
中学受験だと、塾から「過去問をとにかく解いてください」と言われて、訳も分からずひたすら解き続けることもしばしば。
もちろん数を多くこなすのは大事ですが、過去問の解きなおしや振り返りの方がはるかに重要です。
今回は見落としがちな中学受験における過去問の活用方法について、現役塾講師の目線から解説をしたいと思います。
中学受験の過去問は何のためにやる?
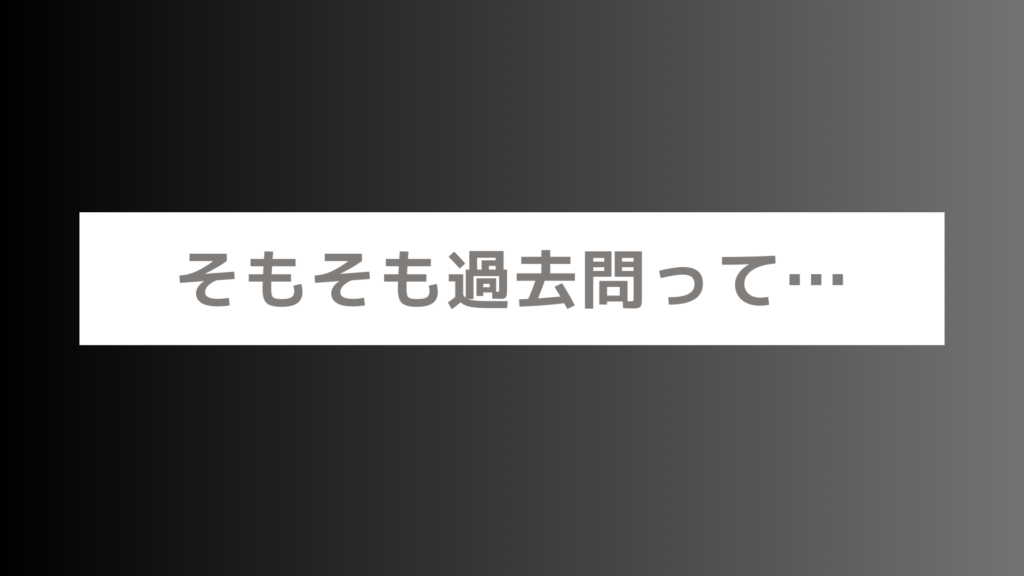
まず、大前提として過去問は本番の出題形式を知るためのツールという風に思ってください。
学校によってはオーソドックスな計算問題が出題されるところもあれば、最近増えてきたように思考力を試す問題を織り交ぜているところもあります。
過去問を使うことによって、その学校がどんな問題を出題するのか、大問の数は何個あるのか、記述はどれくらい問われるのか…などなど様々な情報を仕入れることができます。
また、実際に問題を解いてみることで自分の弱点が可視化されたり、問題に対しての時間配分の戦略も立てることができます。
過去問を演習して問題の形式を知り、合格点と現在の実力との乖離度を把握する。そして、復習する中でそのギャップを埋めていくというのが過去問を通してやっていく作業です。
でも、どのように過去問の解きなおしをしていけばいいのでしょうか。次は中学受験における具体的な過去問の振り返り方について紹介したいと思います。
中学受験における過去問の解きなおし方
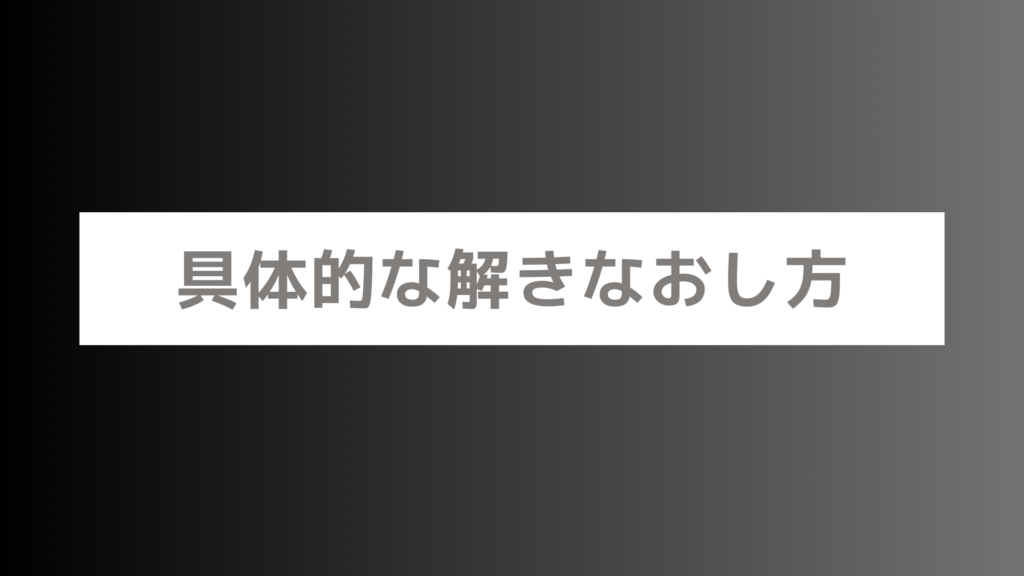
せっかく入試の過去問にチャレンジするなら、単に間違えた問題を解きなおして終わりというのは非常にもったいないです。
まずは算数・国語・理科・社会の各科目について次のことをしっかりと意識してください。
・解き直し用の専用ノートを作る
・弱点分野の補強までがセット
まず、必ず過去問用の「解きなおしノート」を作成してください。ノートには間違えた問題の解きなおしと、どうして間違えてしまったのか自分なりの分析を少しでも書くようにしてください。
例えば、算数の問題で解けなかったものがあるなら、ダイアグラムの考え方が分かっていなかったから解けなかったのか、問題文をよく読んでいなかったから勘違いをしたのか、計算の段階でミスをしたのか、時間配分が良くなかったのか…などなど解けなかった要因が必ずあるはずです。
その要因を自分でメモして可視化することで、次は同じ失敗をする確率を減らすことができます。小学生が自力で徹底してやるのは難しいですが、ちょっとでも意識してほしいポイントです。
また、できなかった理由がその分野の理解度の低さのせいなら、同じよう問題を使って復習することが大事です。
例を挙げると、理科の電流の問題が解けなかったら、別の問題集も使って電流の分野を徹底的に復習するといったように、分野ごとのブラッシュアップをしていきます。
特に、毎回間違えてしまう分野はコアとなる考え方自体がちゃんと理解できていないというケースが多いです。
「塾の先生がそう言っていたから」ではなく、「並列回路は電熱線の幅が太くなるのと同じで、電気が2倍流れやすくなるから抵抗は半分になる」といったような説明が自分で出来る段階まで落とし込みましょう。
中学受験過去問の各科目ごとの振り返り方
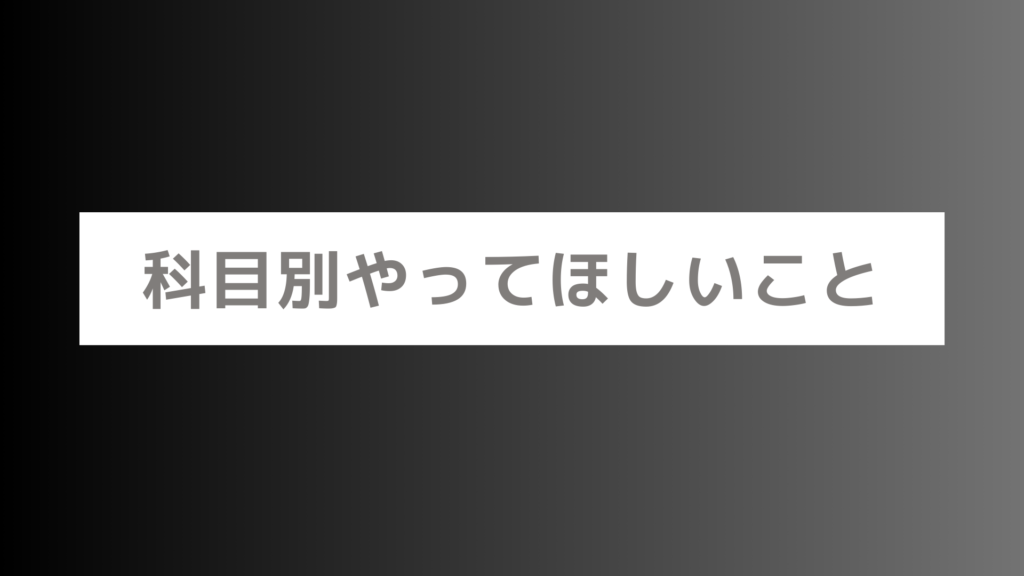
振り返りノートを作り、過去問で出来なかったのと同系統の問題を対策するのが大事ということは分かってもらえたと思いますが、各科目ごとに押さえておいてほしいポイントがあるので紹介します。
国語
個人的に一番復習が難しい教科が国語ではないかと思っています。
というのも、問題を解いて解説を読むと「分かった」気になってしまい、それ以上復習する気が起きないからです。
でも、国語は多くの学校で算数と同じ比重で点数が配分されている科目であり、合格に直結するからこそしっかりと復習の仕方を身に付けてほしいです。
具体的な復習方法は、各設問の根拠を考える・間違った選択肢はどこが間違っているかを考えるです。
読解問題においては、ただ選択肢が合っていた・間違っていただけではなく、「どうしてそう言えるのか」を整理していく力が必要不可欠です。
説明文にせよ、小説にせよ、随筆にせよ、必ず根拠となる箇所が本文中に書いてあります。それを正確に見つけられているかを復習の時にチェックしてください。
また、復習の際には各選択肢で間違っていたものも検討し、どこがダメなのかその理由を考える癖をつけましょう。面倒に感じるかもしれませんが、この訓練を続けていくことで点数が安定していきます。
当たり前ですが、知識問題や漢字で失点が目立つ場合は危機感を持って復習しましょう。合格のためにはこれらの問題は落とせないので、分からなかった漢字などは過去問ノートにまとめておくこと。
算数
算数は苦手分野を1つずつ潰していくことが合格への近道です。
声の教育社などの過去問を見ればどの分野が出題されやすいのかを分析して載せてくれています。
そちらや模試の結果を参考にしつつ、志望校にも出題されるが苦手で毎回落としてしまうという分野を徹底的につぶしていくことが必要です。
大切なのは、どこが苦手でまだ身に付いていないのかを可視化する工夫をすることです。
例えば過去問を解きなおした後には、できなかった問題の類題を他のテキストから持ってきて扱ってみる、少し時間をおいてからもう一度解いてみて本当に定着できているかをチェックするという学習をしていただきたいです。
特に特殊算と呼ばれる中学受験に独特の問題や、割合や速さの問題などは早い段階で解法をインストールしてそれをアウトプットする訓練を通じて定着させていくことが必要です。
女子校はまだ算数が簡単めという傾向はありますが、どの学校を受けるにせよ、2科受験・4科受験をするにせよ算数は最重要になりますので、一番力を入れて復習していただきたいです。
理科
理科も算数と同様に苦手分野ごとに潰していくことが必要です。
理科の場合は生物・地学・化学・物理という4つの分野に分かれており、生物・地学はほとんどが暗記がものをいう世界になり、化学・物理では複雑な計算も含まれて来るというイメージです。
正直、化学と物理の計算問題は苦手な子にとっては苦しい分野だと思いますので、まずは生物・地学分野を中心に知識問題を押さえていくのが良いと思います。
近年は思考力系の問題の出題が多くなってきているとはいえ、知識問題は絶対に落とせない分野。そのため、過去問で知識の抜け漏れがあれば真っ先に確認してほしいです。
下記のテキストはあのサピックスから出ている教材ですが、これ1冊をしっかりとやりこめば知識問題の穴はなくなると思います。むしろ動物の身体の部分などは詳しすぎるくらいです。
物理や化学の計算問題もちゃんと収録されているので生徒にも補助教材としておすすめしています。併せて検討してみてください。
社会
社会は大きく分けて地理・歴史・公民の3分野に分かれており、90パーセント以上が暗記できているかできていないかで決まると思います。
さらに問題の傾向を分けると、単純な知識の暗記と記述問題、資料の読み取りの3つに集約されます。
過去問を解いた際に見てほしいのは、上記3つのどこが弱いのかです。
単純な知識問題と記述の大半は今まで使ってきたテキストを復習することで、ブラッシュアップすることができると思います。先ほど理科で紹介したコアプラスのようなテキストも知識の定着には良いかと思います。
また、過去問を復習する際に特に意識してほしいことは、記述問題がちゃんと理由も含めて答えられるかを見るということです。
例えば、「井伊直弼が桜田門外の変で暗殺されたのはなぜか」という問いかけに対して、日米修好通商条約の内容と関連付けて答えられるかどうかなどです。良く分かっていない部分はテキストを見返して流れをノートにまとめるのが効果的な復習だと思います。
資料の読み取り問題に関しては、それだけがまとまっている教材が少ないので対策が難しいのですが、公中検模試(公立中高一貫校適性検査対策模試)や公立中高一貫校向けの対策問題集が参考になるかもしれません。
復習に不安を感じるなら
テキストを読んで振り返るだけではどうしても苦手分野を攻略できない、不安が残るという方は、その分野だけプロの授業を受けてみるのもおすすめです。
具体的にはスタディサプリの映像授業はスキマ時間に勉強でき、月額2,178円から受講できるため不安箇所を仕上げるという意味では最高のコストパフォーマンスを発揮してくれ、非常におすすめです。
【スタディサプリ】中学受験の賢い使い方とは?活用法を徹底紹介します。>>
過去問の振り返りにおける注意点
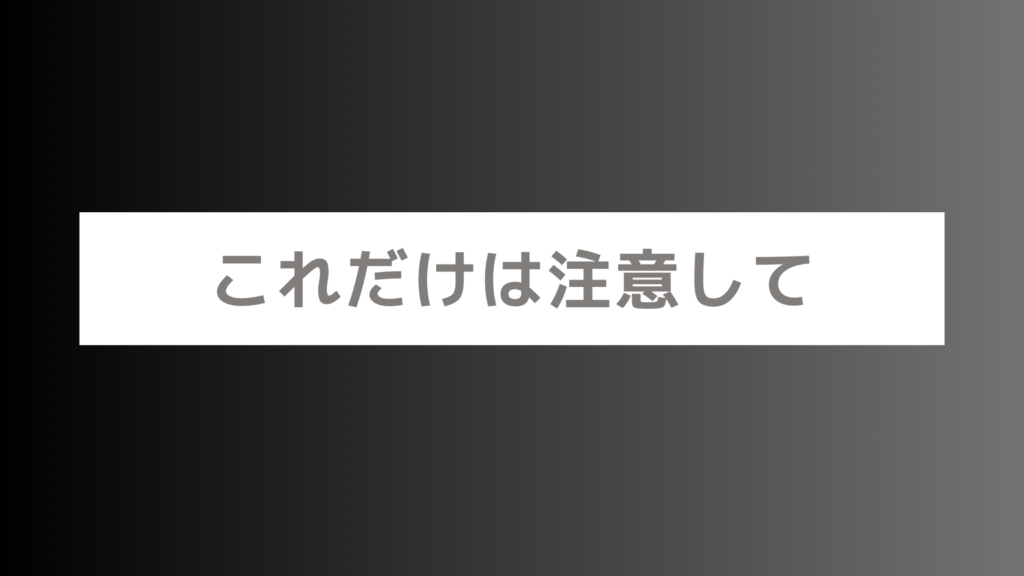
各科目について過去問を通じた復習方法をお伝えしましたが、注意してほしいこともあります。それは以下の3点です。
1.あくまでも理解度を重視する
2.完璧を求めない
3.弱点から目を背けない
まず、過去問をやってできない問題があっても焦らず、自分の弱点を淡々と潰していくという意識が必要です。
特に受験が近づいてきて全然できない分野があると不安に思う気持ちは痛いほどわかりますが、本番までにしっかりと理解して次に同じようなタイプの問題が来たときに対応できるようにしてください。
焦ってしまい、次から次へと新しい過去問を解くことは言語道断です。しっかりと見直しと復習の時間を確保して知識や解法を定着させることが最重要課題です。
また、完璧を求めない姿勢も非常に重要です。
受験は100点を取る勝負ではなく、合格点を取る勝負です。中には一握りの天才しか解けないような難易度の問題も出題されます。
過去問を解きなおす際は徹底的に復習してほしいのですが、明らかに自分のレベルとは合っていない問題は潔く切り捨てて、時間をかけすぎないようにしてください。
最後に、一番大事なのは自分の弱点から目を背けないことです。
よくあるのが、自分が好きであったり得意であったりする科目ばかり勉強してしまい、弱点の克服がおろそかになってしまうケースです。
それでは総合的な点数の伸びは緩やかになってしまい、受験で勝利を勝ち取るのは難しくなってしまいます。
どんな方でも苦手分野は必ずあるので、過去問で出来なかった部分とはしっかりと向き合うようにしてください。
まとめ
中学受験の過去問は、出題範囲と自分の実力とのギャップを知るためにあります。
最悪なのは過去問を解きっぱなしにしてしまい、分析と弱点補強を行わず、何となく勉強した気になってしまうことです。
必ず過去問専用の解きなおしノートを作り、自分の弱点と向き合って克服するようにしてください。
もちろん、できていないことと向き合うのは苦しい戦いになりますが、最後に笑うためには絶対に避けては通れません。歯を食いしばって、苦手を潰していってください。

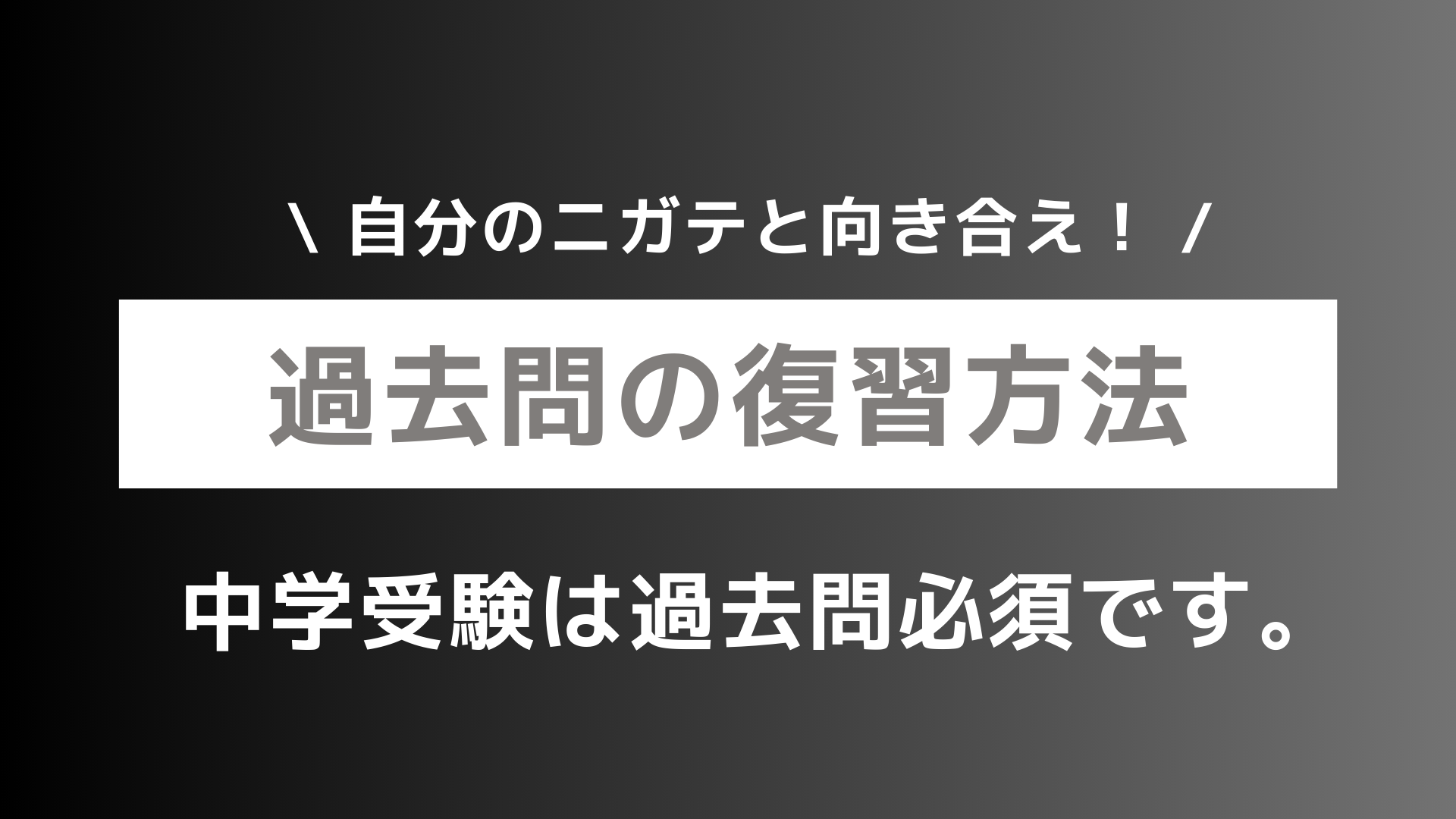




コメント