中学に入ってから突如現れ、大学受験まで付きまとう悪魔の科目「古文」。なんだかよく分からないまま付き合いが始まり、受験の前に泣く人も多いのが古文です。そんな古文に対しては「勉強する意味が無いんじゃないの?」という意見もよく見かけますし、実際に僕自身も昔はあまり意味を見出せませんでした。
結論から言うと、高校生が古文を勉強するのは受験で有利になるからに尽きます。多くの人にとってはコスパ良く勉強して大学に入るためのツールとして割り切るのが良いと思います。でも同時に、教える側になって分かったことは古文はとても面白い科目だということです。この記事では古文の勉強の意味と楽しみ方までをお伝えしたいと思います。
古文は意味がないという意見
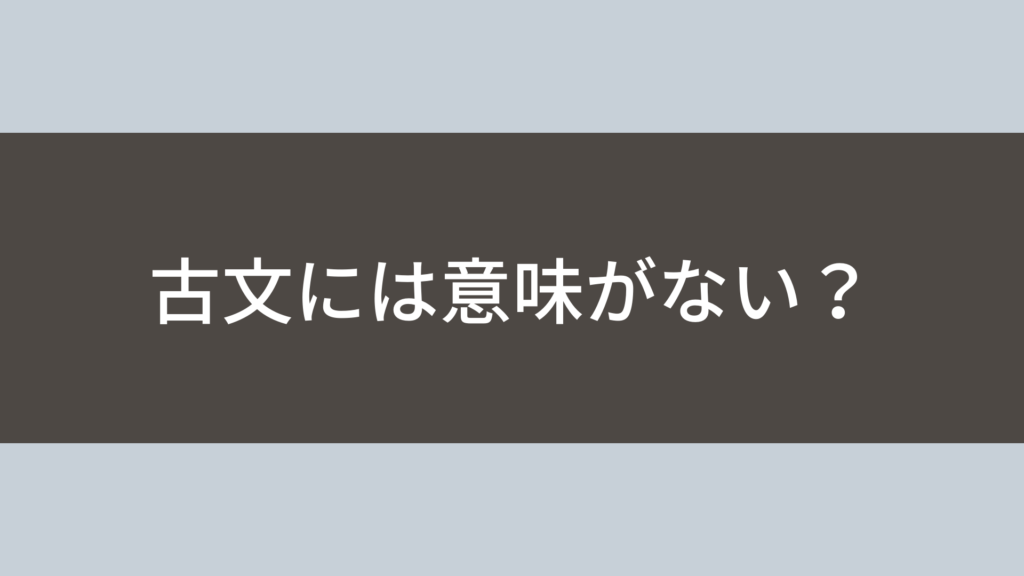
まず、古文に対するマイナスな意見をざっくりと見ておきましょう。
・日常生活で全く使わない
・登場人物の行動が意味不明すぎる
・古文単語や文法が嫌い
・理系なので正直いらない
・模試だと時間なさ過ぎて無理ゲー
思いつくものと僕が実際に感じていたところを挙げてみるとこんな感じでしょうか。
まとめると、将来的に全く役にも立たなそうなものを無理やり学校でやらされるというのが古文嫌いの大半を占めているように感じます。あとは、旧センター試験や共通テストでは古文は現代文の後にあり、結局圧倒的に時間が足りない言う理由で勉強する気が起きない人も多いと思います。
これらの意見はとてもよく分かりますし、僕も学生の時は「なんでこんなの入試に必要なん…?まぁそこそこ点が取れればいいや。それより英語やろ。」みたいな感じで後回しにしていました。
古文を学ぶ意味は2つだけ
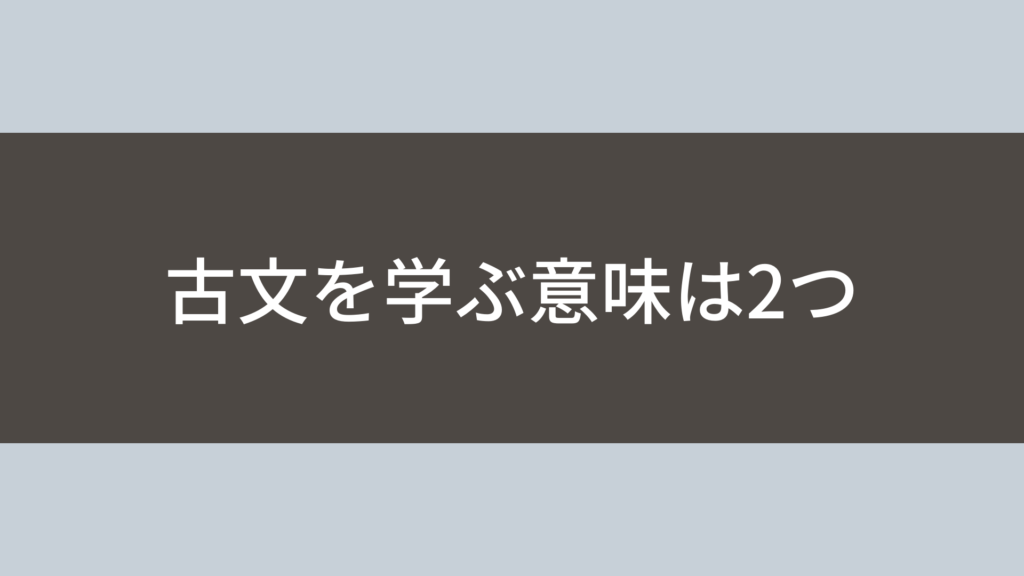
で、実際に古文を学ぶ意味は何なのかというと以下の2つになると思います。
①現実問題として受験に必要で簡単な科目だから
②見方さえ変えればとても面白いから
正直に言うと受験には必要で、実生活には直接は役に立ちません。(でもこれを言い出したらほぼ全ての勉強が役には立たないですよね…)それよりも、古文を通じて楽しみや異なった物の見方を得ることの方が重要だと思います。まずは古文を勉強する意味について上記2点を確認しておきましょう。
①現実問題として受験に必要で簡単な科目だから
ある程度のレベル以上の大学を目指す人は古文から逃れられません。もちろん、理系の私立に進むといった場合は古文は使わないかもしれませんが、国公立志望の場合は理系でも多くの学校が古文を必要とします。こう聞くと「終わった…」となる方も多いと思いますが、古文はかなりコスパがいい科目です。
というのも覚えることが非常に少ないからです。単語なら300個ほど、熟語などを入れても600個ほど覚えるだけでどんな大学にも対応できますし、暗記すべき文法事項もメチャクチャ少ないと言えます。
英語と比べると一目瞭然ですよね。一般的に英単語だったら5,000~7,000ほどを覚えなければならないと言われており、文法も分詞構文や関係詞、倒置などなど高度なものが欲求されています。
その割にみんな敬遠する科目なので勉強すれば差が付きやすいとも思います。このため、受験において古文は取り組むべき科目なのです。
②見方さえ変えればとても面白いから
とはいえ受験に必要と言っても勉強を楽しめなければ意味がないと僕は思っています。どんな科目もそうですが、楽しまずにただ勉強するというのはキツイですし受験勉強が終わったとたんに詰め込んだことは全部忘れてしまいます。
正直受験生の頃は何が面白いのか分からなかったですが、教える側となり古文をしっかり勉強してみると2つの意味で面白いということが分かりました。1つ目は単純に読み物として面白く、漫画やアニメあるいはドラマのようにストーリー展開が気になるという点で、もう1つは言語や文化のギャップを感じられる面白さがあります。
…と言われても「古文は面白くない」という固定観念にガチガチに縛られている方も多いと思います。これらの楽しみ方については以下で詳しく見ていきましょう。
塾講師になって分かった古文の楽しみ方
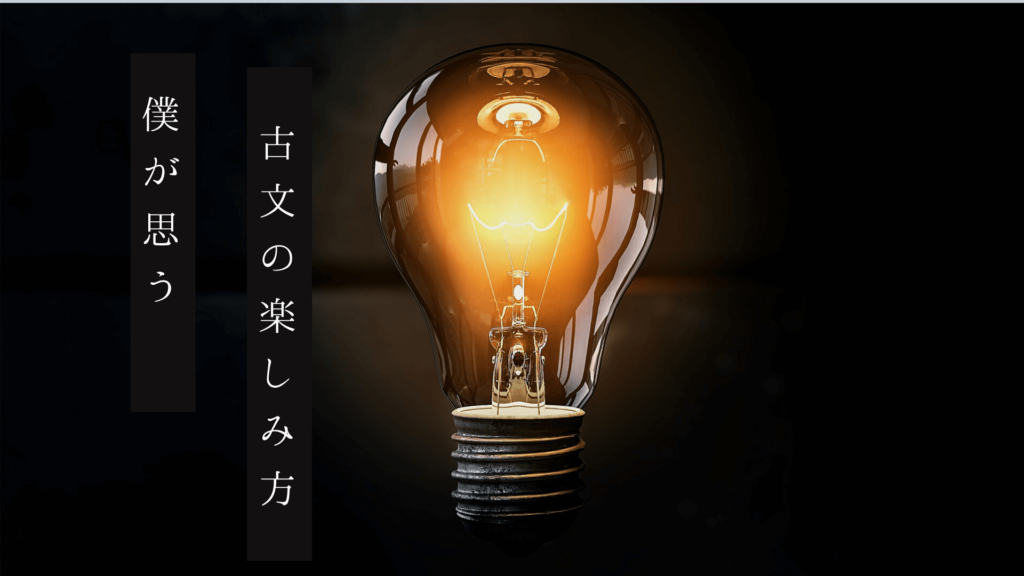
では、古文の楽しみ方とは一体何なのか。ここでは僕なりに古文を楽しむコツを2つ紹介したいと思います。
①:当時の時代背景はそういう設定と理解する
古文の世界の人たちって、マジで今とは常識が違います。男性が女性のもとに通って結婚するとか、いい歌が詠めないとモテないとか、急に仏様のスーパーパワーが発動したりとか…今で考えるとよくわからんことだらけ。
僕たちは「古文に出てくる人たちも日本人なんだよなぁ…」という目線で読んでいるので様々なギャップに対して、「それは考えられんわ…(困惑)」となんだか引いてしまうのではないかと思います。
でも、僕は古文は異世界転生もののラノベくらいの感覚で読んだ方が何千倍もいいと考えています。今の日本人とはまったくちがうけど、なんかそういう設定のもとで書かれた物語なんだな~くらいでちょうどよく、変に現代日本の常識を持ち込み過ぎない方がいいです。
例えば、「源氏物語」だったら光源氏という超絶チートイケメンが無双する物語ですし、「沙石集」なら仏教ベースのあり得ないファンタジーだし、「徒然草」なら引きこもっているワイが世の中の無常を語るンゴwみたいな感じで僕はとらえています。
漫画やアニメだってそんな感じで「あり得ないこと」がフツーに起こっていますよね。でも僕らはそれに違和感もなく「そういう設定なんだ」と納得して楽しんでいます。古文の場合も同じで当時の常識や考え方、信仰を知り「そういう設定(考え方)があるんだ」と理解することで楽しめるようになると思います。
②:新たな言語として学びギャップを楽しむ
さきほども触れましたが、古文の世界は現代日本とはかけ離れています。それは言葉の使い方についても同じで、例えば「かなし」という言葉は基本的に「悲しい」という意味ではなく「愛おしい」という意味で使用されています。
なので、古文を学ぶ際には英語や中国語やロシア語のように完全に別の言語だという意識を持つことが必要です。別の言語を勉強する楽しさは「僕たちとは異なる世界の切り取り方」を学べることだと思っています。
この辺を詳しく説明しているとソシュールとか言語論の難しい話になってきてしまうので今回は割愛させていただきますが、異なる言語の間には表現の仕方や物の捉え方のギャップが存在しそれがとても興味深いと思います。
そういった考え方を学ぶと「あぁ、僕らの考え方も1つの考え方に過ぎないんだなぁ」と自分を対象化することができ、自由な考え方をすることができるのです。特に高校生までは英語以外の外国語を学ぶ機会があまりないため、異なる価値観を知るという意味でも古文はとても良いツールだと思います。
まとめ
古文は多くの受験生から嫌われている科目ですが、受験科目と考えると単語や文法も覚えることが少なく、真剣に勉強する人も少ないので差が付きやすい「コスパが良い」科目だと思います。この点で古文は勉強する価値がありますね。
しかし、単純に暗記をしてよくわからない文章と向き合って…というのは苦行でしかありません。受験科目全般に言えることですが勉強することに意味や楽しみを見出すことが大切です。
古文はストーリーが結構ぶっ飛んでいるのでそういうフィクションだと思って僕は読んでいます。また、昔の日本人とのギャップも感じられて自分の常識を相対化することができるというのも古文の魅力ですね。皆さんも捉え方を変えて、楽しみつつ古文を勉強できるようになると成績も自然と上がっていくと思います。
古文の具体的な勉強方法については以下の記事で詳しく解説しているので気になる方は覗いてみてください。

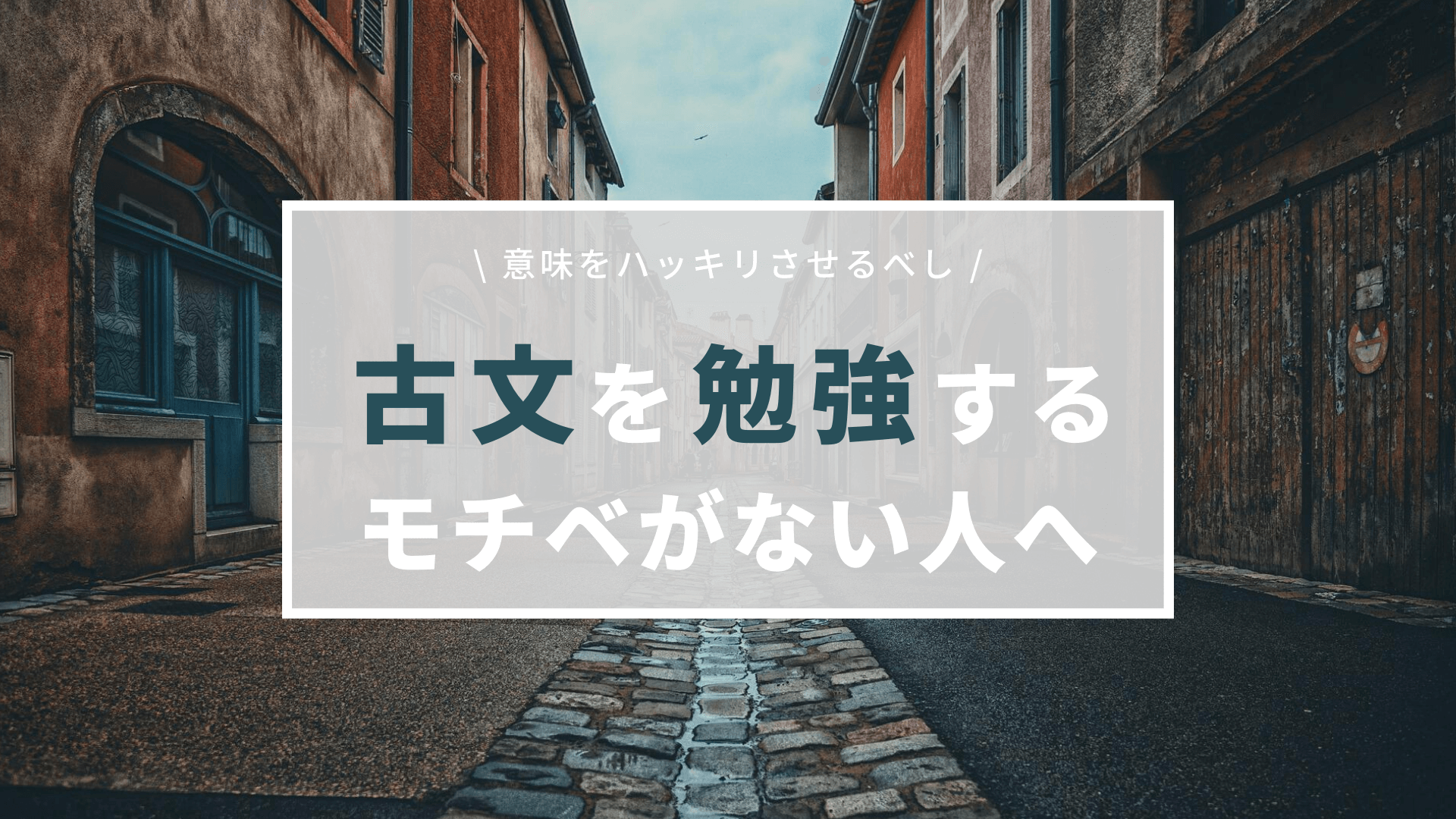


コメント