頻出の古文単語の1つ「あさまし」。よく見かけるけど意味があまり分かっていないという方も多いのではないでしょうか。状況をイメージできないとなかなか古文単語は覚えられませんよね。
「あさまし」の使い方や意味について意味や例文をお伝えしたいと思います。どんな状況で使うものなのかしっかりとインプットしていってください。
あさましの意味とは?
まず、僕が使っている「読んでみて覚える重要古文単語315」で「あさまし」の意味を引いてみると次のように載っていました。
①:驚くほどだ
②:あきれるほどだ
③:情けない
コアとなる意味は「驚きあきれる」で予想もしなかったことに驚く様子。基本的には悪いことに使われますが、古文では良いことに対しても使われる点に注意。辞書によっては「みっともない」「見苦しい」といった訳をあてているものもあります。
※ちなみに派生表現の「あさましくなる」というものもあり、こちらは直訳すれば「情けない状態・見苦しい状態になる」という意味ですが、「亡くなる」という意味になるので注意。「死ぬ」の遠回しな慣用表現ですので余力ある人は覚えておきましょう。
あさましの使い方・例文
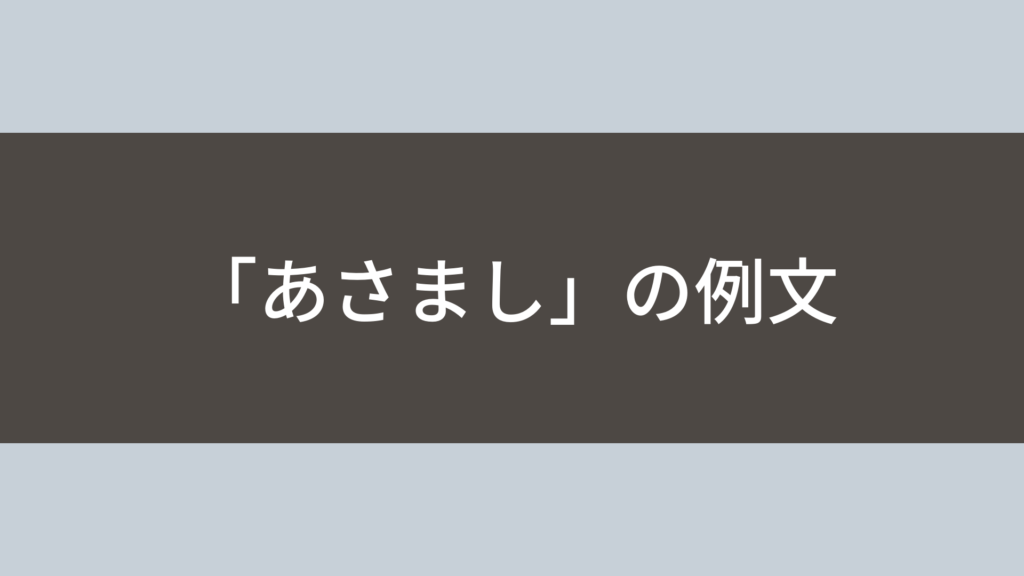
コアとなる意味を押さえた後は例文で使い方を確認していきましょう。
①:あさまし=驚く、驚きあきれる
「思はずにあさましくて、『こはいかに、かかるやうやはある』とばかり言ひて」
→思いもかけず、驚き(あきれて)「これはどうしたことか、このようなことはあるだろうか、いやあるはずはない」とばかり言って
かくあさましくて持てきたることをねたく思ひ、
→このように驚いたことにも(蓬莱の球の枝を)持ってきたことを忌々しく思い
②:あさまし=あきれるほどだ
かくあさましきそらごとにてありければ、
→このようにあきれるばかりの嘘であったので
二年が間、世の中飢渇して、あさましきこと侍(はべ)りき
→2年間、世の中が飢餓で、あきれるほどの(ひどい)ことがございました。
③:あさまし=情けない、見苦しい
わがもてつけたるをつつみなく言ひたるは、あさましきわざなり。
→自分が使い慣れている言葉を遠慮もなく言うのは、情けないものである。
一といふ文字をだに書きわたし侍らず、いとてづつに、あさましく侍り。
→「一」という文字ですらずっと書かないでおりまして、大層下手で情けなく(見苦しく)ございます。
あさましの音便化「あさましう」にも注意
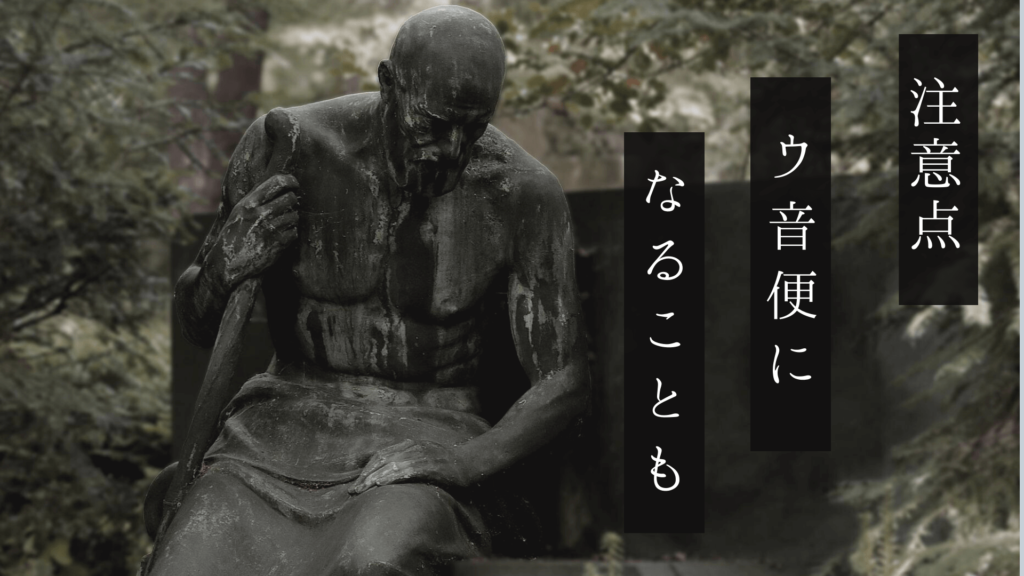
意味は例文で押さえられたと思いますが、「あさましう」と出てきたときにビビらないようにしてください。例えば次の例文を見てみましょう。
あさましう、こはいかなることぞと思ひ惑はるれど、
→驚いた、これはどのようなことだと動揺せずにはいられないが
ここでは「あさまし」がウ音便となって「あさましう」になっていますが意味は全く同じです。古文では言いやすいように音便化が起こるということもセットで覚えておいてください。
まとめ
「あさまし」の意味は①驚く②あきれるほどだ③情けない・見苦しいまで押さえておけばOKです。今回は色々例文を紹介したので実際にどんな場面で使われるのかしっかりイメージできるようにしていきましょう。
また、ウ音便となって「あさましう」と出てくるケースがあること、「あさましくなる」は「亡くなる」という意味の慣用表現であるということも覚えておくと色々な場面で役立ちますよ!


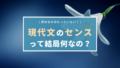

コメント