古文の勉強をしっかりと続けていると出会うことになる謎の係助詞「は」と「も」。
係り結びのところでも習わないし、正直どこで出てくるのか分からないですよね。今回はちょっと細かい話ににはなりますが、係助詞の「は」と「も」について知っておきたいことをまとめました。
古文の更なるレベルアップをしたいという方はぜひ最後までお付き合いください。
係助詞「は」と「も」の意味は?
まず、「は」と「も」ですが、これは間違いなく係助詞です。ただ、「ぞ・なむ・や・か・こそ」と違うのは「は」と「も」は係り結びを作らないというのがポイント。つまり文末は連体形や已然形になることはなく、終止形のままです。
では、係助詞「は」と「も」はどのように訳していけばいいのでしょうか。正直に言うと、これらは全くそのまま「は」や「も」で訳を充てれば大丈夫な場合がほとんどです。
一応次の訳も知っておくといいですが、「は」や「も」で訳してみて何かちょっと不自然な場合に検討するくらいでいいでしょう。
・係助詞「は」のその他の訳
「~ならば(順接仮定条件)」
「~よ(詠嘆)」
・係助詞「も」のその他の訳
「せめて~だけでも(最小限の願望)」
「~もまあ(強調)」
ただ、これらの中でもちょっと難しいものがあります。それも一応紹介しておきます。
「はも」という連語について
古文の中には「はも」という連語が存在します。これに関してはほとんど出ることはないと思いますが、興味がある人は以下のように押さえておきましょう。
・文中の「はも」…係助詞は+係助詞も
・文末の「はも」…係助詞は+終助詞も
文中にある場合の「はも」は今回紹介している係助詞が2つ組み合わさった形です。意味としては強意となり「~は」と訳しておけば大丈夫です。
一方、文末にある時の「はも」は係助詞+終助詞となります。意味は詠嘆ですので「~よ」「だなぁ」と訳せればOK。細かいですが気になる方は押さえておきましょう。
そもそも終助詞って何?という方は覚えておくべき終助詞を別記事にまとめているのでコチラも参考にしてみてください。
>>【古文】終助詞とは何か?わかりやすく意味を解説してみた。
係助詞「は」と「も」の例文

実際にこれらの係助詞がどのように使われているのかを見ていきましょう。
・おぼつかなくは思えども
(気がかりには思われるけれども)
・いかがはせむは
(どうしようか、どうしようもないよ)
・男も女も驚きけり
(男も女も目を覚ました)
・山ほととぎす一声も鳴け
(山ほととぎすよせめて一声だけでも泣いてくれ)
・限りなく遠くも来にけるかな
(この上なく遠くまで来てしまったなあ)
上で紹介したような例文を覚えておけば係助詞「は」と「も」は攻略できると思います。あまり問題として聞かれることは少ないと思いますが、古文の読解の中で出てきたら判別できるようにはしておきましょう。
まとめ
「は」と「も」は係助詞ですが、「ぞ・なむ・や・か・こそ」のように係り結びを作らないのがポイントです。
基本的には「は」「も」とそのまま訳しておけば事足りる場合がほとんどですが、詠嘆や強調など独自の用法もあります。まずはそのまま訳してみて、不自然な場合は他の訳を充てられないか考えるようにしてみてください。
より古文をしっかり勉強したいという方はスタディサプリの授業も超おすすめです。神講師が映像授業でわかりやすい解説を提供してくれます。体験もできるので迷っているならぜひ試してみましょう。


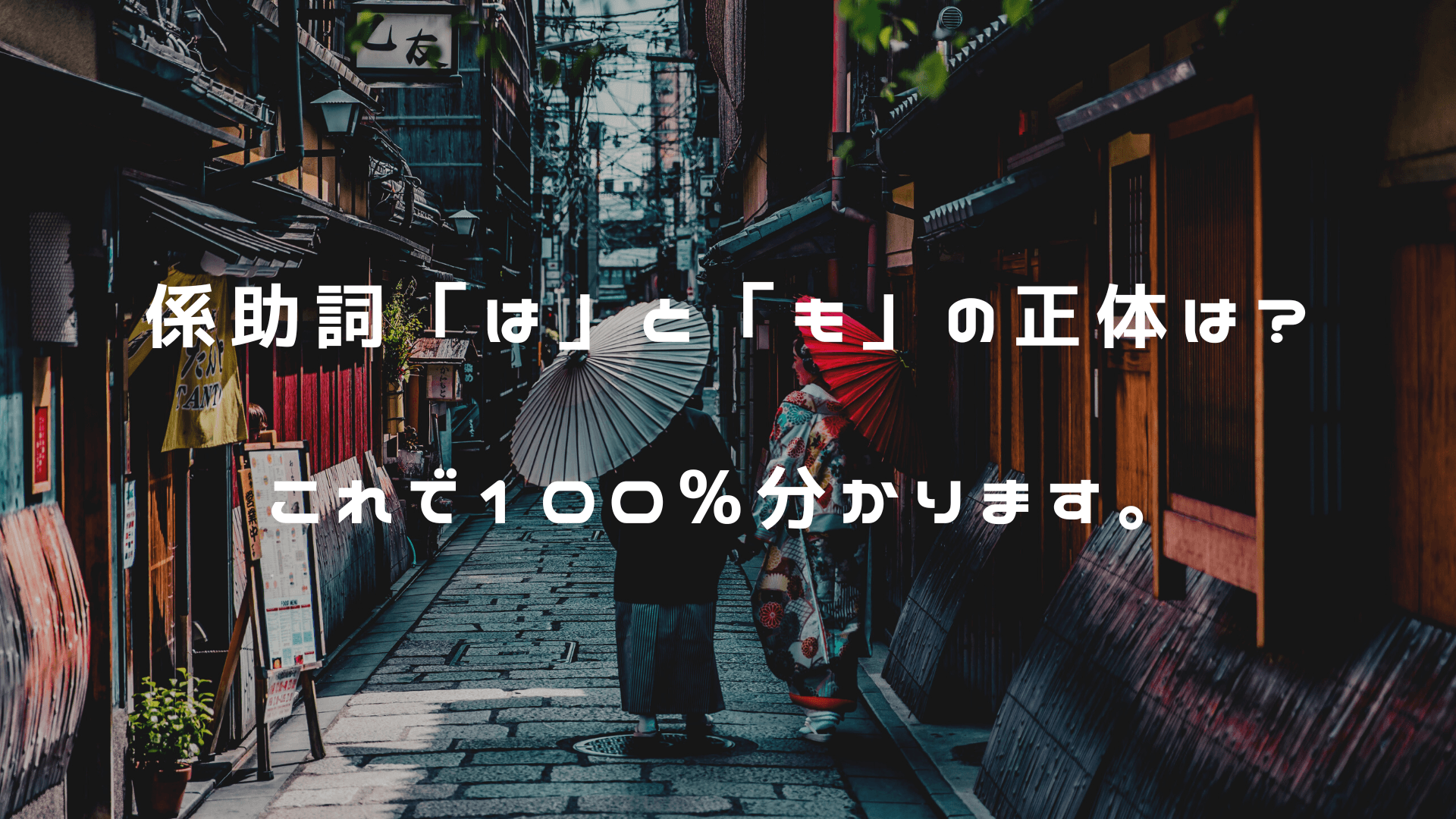

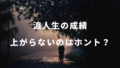
コメント